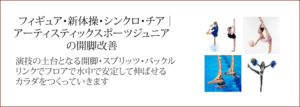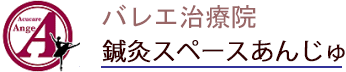バックルと前後開脚はつながっている
開脚が完成するには、脚だけみていては足りないと言うことを、前回言いましたが、バックルこそ、まさに脚だけでは完成しないのです。
通常人のカラダは前に向かって進むので、後ろに脚を高く上げるというのは、日常生活にはでてきません。
新体操、フィギュアスケートでは、脚を後ろにあげてその脚を手で持って背中を反らせることが技としてあるので、当然、小さい頃から練習する訳です。
一般的には、立った状態で脚を後ろにほうり投げるようにしてバットマンし、その脚を手で捕まえる練習をするようなのですが、これができる派と苦手派に分かれるんですね。
何度か練習してコツをつかむ子は、一つにはカラダの感覚が優れているタイプが多いです。
どうやって後ろに脚を出せば、頭の後ろに持ってこられるか、手でつかむには、肩の位置をどういう風にもっていけばつかみやすいのか、が試行錯誤しているうちに掴める子、です。
そこまでカラダの感覚が強くなくても、コツコツやれるタイプは、何度も何度も頑張るのですが、ここで分かれやすいのが、元からのカラダの個性です。
ジュニアそれぞれのカラダの柔らかさは似ていても、軸がしっかりとりやすいタイプ、足がしっかり地についているタイプ、上半身のスクエアが安定しているタイプは、時間をかけていけばやれるようになっていきます。
このカラダを動かすタイミングを見つけたり、出しやすい方向を探す感覚は、本当にさまざまで、諦めないで少しずつ変えていけるタイプは、年数がかかっても克服していけるのですが、ここで何年もやっていてどうしても後少し手が届かなくて完成しない、というタイプの方も結構いるのですね。
学年があがって、筋力や体力がついてくるとできるようんなるケースもありますが、目の前の試合に出ることになって、でも後少しが完成しなくて、、、、と悩んでしまう。
こういう時には、別の方向に目を向けてみると、案外スルッとできるようになるものなんです。
新体操やフィギュアをしているジュニアは、バレエだけしているジュニアよりも筋力が強いタイプが多いです。
筋力はあるのに後一歩がうまくいかない理由は?
・力で上体をねじってもってこようとする
・脚をあげることだけに意識がいって踏んでいない
これがとても多い。
バックルは、違う方向から見れば、スプリッツで上体を後ろに反らす形とほぼおなじですよね。
なので、まず、スプリッツが本当に力が抜けてキチンとできているかを診ていきます。 すると、バックルが苦手な子は、やっぱりスプリッツもどこかつっぱってやっているのです。
なので、基本の開脚、スプリッツの完成度をあげていく訳です。 開脚した時の骨盤の位置、そこから立ちのぼる脊柱のライン、更に上にのっている肩や頭の位置、又、脚は付け根からつま先まで力が抜けているか、これをひとつひとつ確認しながら、開脚、スプリッツを完成させていく訳です。
そうすると、大抵は腰があがってきて上半身が更にたってくるようになります。そうしたら次の段階、色々なシチュエーションでパンシェをさせていきます。
深くパンシェするには、上半身のスクエアが安定していることが不可欠。怖くて、首がすくんでしまうようだと、バックルの時もしっかりスクエアがキープされてない。
色々なパンシェを繰り返し、開脚スプリッツも、足の下にブロックを置いて、ハムストリングがより伸びるようになってくると、小学生だとほぼ、バックルまで完成していきます。
この時に足で立つ位置、腕で足をつかむ位置、背中の位置は、骨のどこで支えるといいのか、そのジュニアのカラダに合わせて、指示していきます。
この筋肉をもっと伸ばして、というと逆に意識して固まりやすいから指標にするなら、断然骨、がオススメ。
もちろん、骨を意識してもらうのも、筋肉を正しく使えるようにするため、そのための姿勢づくりの土台にするため、です。
反対に、一番オススメしたくないのは、どこを意識すればいいかも指摘せずできるまで何度も何度も繰り返しさせる、とか、開脚、スプリッツだと、足を椅子の上にのせて上から押し続ける、など。 これらはできるなら避たほうがいいです。
がんばったあげく、腱や靭帯を切ることにつながりやすいからです。
ジュニアによっては、どうしてもバックルを完成させたいと無理に力で引っ張って、あばらを開いてしまったり、肩を歪めてしまったり、側弯なっていたするケースもあるのです。
一生懸命やってきたのに、カラダをゆがめてしまっては、何のために練習してきたのか分かりませんね。 やっていて痛いのだと、自主練だって腰が引けます。 上から乗っかって押したり、脚だけをグイッと押し上げるのではない、スンナリバックルにいく方法だと、自主練も格段にやりやすくなります。
バックルで悩んでいる方はご相談ください。