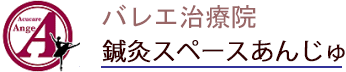何故あなたは内肩・巻き肩になる?解剖学が解く秘密と新常識で美しい姿勢へ
今週日曜日5月25日、日本バレエワークアウト協会のインストラクター更新研修がありました。
今年で14年目になる解剖学講義を行ってきました。今回のお題は「内肩・巻き肩」
毎年いろんなご要望いただくのですがこのテーマはなぜか初めてでした。
クラスを教えているインストラクターさんは、生徒さんに肩を上げないようにアドバイスしています。けれどなかなか生徒さんの内肩・巻き肩が変わらない…こんな悩みがあるんです。
生徒さん自身も内肩・巻き肩にするつもりはない…はずです。でもそうなりやすい構造がある、この点を解説してきました。
内肩・巻き肩と言うとスマホ首も関係はあります。固まりやすい肩甲骨とも関係がありますけれど実は大事な点が見落とされているのです。それが
腕と脇・胸の構造
今回は図を沢山乗せた資料を作って解説をして行きました。
一番のポイントはこちら↓
日本人は肩幅が薄く狭い骨格をしているという特徴がありこの骨格の特徴が内肩・巻き方にとても関係がある
ということです。
ただとてもほっそりしているのに内肩・巻き肩になってない人がいる、比較的ボディが厚めなのに内肩・巻き肩になっている人がいる。
いろんな個性の方がいます。これはひとりひとりの骨格、筋肉だけでなくカラダの使いかたのクセも関係があるのです。
そして、大切なのは足や脚のことばかり考えないで腕と体幹を繋げて踊ることです。
ニューヨークスタイルバレエワークアウトにはこの腕をしっかり使うエクササイズがたくさん含まれています。
そしてチェアバレエエクササイズも同様にポールドブラをたくさん使います。
その利点をしっかり生かして行けるようなアドバイスを加えて講義終了しました。
腕と体幹については本当にひとりひとりのカラダの個性によってハマるところがみつかると動きやすなる傾向があります。
クラシックバレエでもジャズダンスでもチアダンス、新体操でもなかなかうまく思うように動けないという方は一度腕と体幹を見直すことがおススメ。
詳しくはお問い合わせください。
またこういう解剖学に興味がある講師の方はこちらにご連絡くださいね。
【著者プロフィール】
市川淑宥子(ようこ)
バレエ治療院あんじゅ院長
日本バレエワークアウト協会理事
鍼灸師/フロアバレエ・バー・アスティエ講師/チェアバレエエクササイズ講師
2008年、当時はなかったバレエ・ダンスのための鍼灸治療をスタートさせ、「バレエ鍼灸」と名付ける。現在も踊りを続ける治療家として、施術・ターンアウト改善、開脚改善などを展開。
著書:『骨盤が立てばあなたの開脚は変わる』
フロアバレエクラス:新宿にて月1回開催中
▶ プロフィール詳細はこちら
▶ Instagram:ballet.ange
本記事では、バレエの解剖学の外部講師として活動する筆者が、踊るためのカラダの仕組みや動きの仕組みをわかりやすく解説します。