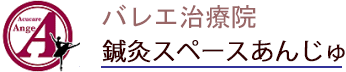出張講座 解剖学+フロアバレエ
出張クラス バレエ解剖学+バー・アスティエ
バレエ治療院あんじゅの土台である解剖学とバー・アスティエクラスを合わせたプログラムが皆さんのお教室に伺います。
5歳からずっと踊っている子なのに脚が太い、つま先を伸ばすように言ってもなかなか習得してくれない、大人の生徒さんに膝痛や腰痛を抱えてレッスンを続ける人が増えてきた、などお教室の先生方の悩みは年々深くなっているように感じます。
それは、昔と比べ、子供たちの体格が変化してきたこと、また、バレエを習うという敷居が低くなり、幅広い年代の方がバレエを習うようになってきたからと関係しています。
子供の頃からずっとバレエを踊りクラスを教えている先生方にとって、自分の伝えたいことがうまく伝わっていないというジレンマが増えています。
それを解決する手法として、更に解剖学とバー・アスティエクラスを合体させた出張メニューをつくりました。
それが、このメニューバレエの解剖学+バー・アスティエクラスです。
教えていてこんな風に悩んでいたりしませんか…
きっかけは2015年6月におこなった「ヘルスケアセミナー2015」。
セミナーの申込者に、ダンサー兼教師の方が数多くいらしたことです。そして先生方の悩みに共通点があることを改めて感じました。
自分のカラダでは分かることが、生徒にうまく伝わらない、その手法を探されている先生方が数多くいる。
自身で解剖学を勉強され、ピラティスなどの資格を取得されている先生方でも、悩みが出てくるのは何故なのか?それは、クラスという性質があるからです。
バーから始まり、センターのアンシェヌマンまで通すのがバレエのクラス。クラシックバレエは、プリエ・タンジュ・デガジェなど一連のパを通さなければ、センターでのアンシェヌマンに移ることが出来ません。
個人指導ならバーだけで終わることも可能ではありますが、通常のクラスではなかなかそうはいかないのが普通。
もうちょっと細かく教えたいと思って、シンプルなアンシェヌマンばかりをつづけると、テクニックは上達してきませんし、ヴァリエーションを踊る際についていけない可能性もでてくる…
細かく伝えるために度々クラスをストップすると、目標としている発表会やパフォーマンスへの指導の点から外れてしまうことにもなりかねません。
バレエのダンスのクラスだからこそ悩んでしまったりするのです。
そんな悩みを解決するメニュー、その内容をご紹介します。
バレエの解剖学+バー・アスティエ|出張クラス その内容
メニューは二部構成となっています。
I バレエの解剖学を体感する
II バー・アスティエクラス
まず初めに、【第1部解剖学の部】から。
例えば、プリエやディベロッペで悩む膝。
膝は横にするのではありません。そう言うと皆さん一様にエッと驚きますが、バレエの解剖学に沿ってプリエすると、膝はちゃんと横を向いていくのです。
それが先生が伝えたい『お膝は横にね』なのですが、このういう部分が伝わりにくいのも又現実。
この出張講座では、先ず、先生が一番伝えたい膝は横に、つま先は外にかかとは内側にというバレエのレッスンで欠かせないポイントを骨格模型をつかったり、映像にあるように実際に皆さんのカラダを動かしたりしながら解明していきます。これが解剖学講座の部分です。
実際のバレエの解剖学講座はこれだけで終わる訳ではありませんが、生徒さんにとって大切な部分を重点的に取り上げてお伝えします。
取り上げる主な部位は、こちら。
バレエの膝・バレエの股関節・バレエの足首
です。
レッスンで大切にしたいこれらの関節で、どこを意識すればいいのかを体感しながらカラダの感覚をつかんでもらいます。
そして、体感した場所を意識しながら実践するのが、【第2部のバー・アスティエクラス】。
Barre au Solのアスティエメソッドは、解剖学的に緻密に構築されており、一つひとつのエグゼルシスは、バレエのパが基本になっています。
関節をニュートラルに踊る感覚を身につけていくこと、それを継続することで、少しずつカラダがアンドゥオールの感覚に目覚めていく瞬間を体感する、これが出張レッスン|バレエ解剖学+バー・アスティエです。実際に参加された方の感想をご紹介します。
体験された方の感想
●勉強になりました。とてもわかりやすく動きのしくみの説明がなされ勉強になりました。
●個別に指導してくださって、参考になりました。他の人への指導を聞いて、見て、というのも勉強になりました。
●“目からウロコ”ということがいくつもありました!
●アンディオールのしかたがよくわかった。
(芸術家のくすり箱主催、ヘルスケアセミナー2015での感想)
このセミナーに参加された先生とその後お話しする機会がありましたが、『動きの仕組みの部分はクラスで取り入れているんですが、生徒にも分かりやすいようです』との感想をお聞きしました。
「ヘルスケアセミナー2015」でおこなった内容の一部はこちらからご覧ください。

目からウロコがおちるプログラム、その根拠
1 開院以来から続くバレエ治療の実績
バレエ・ダンスの3大障害とも言える膝痛、股関節痛、足首の捻挫やアキレス腱周囲炎を多数治療していきた経験から、誤解が生まれるカラダの仕組みが分かってきています。
2 1997年からつづくバレエの解剖学への取り組み
治療で治っても、またプリエをすると再発する…その流れを止めるためには、誤解が生まれてしまうカラダの仕組みを解剖学的に分解して体感してもらうことが大切です。
3 バレエジュニア指導の実績
開院してしばらくして中高生で痛みを訴えて来院するケースが増え、その後、ターンアウトアップ+プラスのメニューがスタートするとプリエが浅い、カエルが苦手、三角骨が出来てしまったなど、踊るカラダに悩みを持つジュニアが沢山来院するようになりました。現在は、コンクールやオーディションを目指しているバレエジュニアも通っており、幾つかうれしい結果につながっています。
4 2012年から始まった外部での講師活動
解剖学講師として、またバー・アスティエ講師として、踊るカラダの仕組みを伝える活動を続けてきた経験から、解剖学とバー・アスティエをあわせて伝えることが踊るカラダのイメージをより鮮明に伝えやすいと実感しています。
これまでの外部講師の実績
2012年より 一般社団法人日本バレエワークアウト協会 (認定講師研修にて解剖学を担当)
2014年 学校法人尚美学園 (領域別舞踊実習)
2015年 NPO法人芸術家のくすり箱ヘルスケアセミナー2015(解剖学的フロアバーでコンディショニング)
2015年 NPO法人バー・アスティエ協会 日本人講師によるバー・アスティエクラス(バー・アスティエと解剖学のコラボ)
これまでのコンクールなど結果
2018年
13回 エヴァ・エフドキモワ記念エデュケーショナルバレエコンペティション ジュニアA第1位
第6回とうきょう全国バレエコンクール 高校生の部 第7位
第6回とうきょう全国バレエコンクール 小学生の部 優秀賞
115回 NAMUE バレエコンクール 神奈川 高学年の部 第4位
オールジャパンバレエユニオンコンクール 努力賞 1名
東京都立総合芸術高校 舞台表現科 舞踊 合格 1名
第23回フラップバレエコンクール プレコンC 優秀賞 1名
第23回フラップバレエコンクール シニア 優秀賞 1名
Kバレエユース合格 1名
2017年
ロイヤルウイニペグバレエ サマーコース ビデオオーディション合格 1名
ロイヤルウイニペグバレエ TTPコース合格 1名
第7回かわさき全国バレエコンクール 第三位 1名
エデュケーショナルバレエコンクール 第四位 1名
第5回フルール東京バレエコンクール 優秀賞第一位 1名
日本ジュニアバレエ 合格 1名
海外留学生サポート(露・加) 2名
2016年
AMスチューデンツ 合格 2名
Kバレエユース 合格 1名
海外留学生サポート(露・独) 3名
2015年
新国立劇場バレエ研修所予科生合格
フラップバレエコンクール B 優秀賞2名
第5回川崎全国バレエコンクール 6位
埼玉県全国舞踏コンクール 奨励賞
ティアラジュニアバレエAクラス 合格
2013年
イン横浜バレエコンクール 赤い靴賞
バレエ解剖学+バー・アスティエ|出張クラス よくある質問
Q どこまで出張が可能なのですか?
A 現在受けられるのは、首都三県です。原則日帰りできる地域で承ります。
Q クラスで何か必要なものはありますか?
A 参加される方には、ヨガマットもしくはタオル、ソックスのご用意をお願いします。
Q どのくらいの年齢から受けられるのでしょうか?
A ポワントをはいて2年以上のジュニアからを対象とします。年齢的には12歳以上が望ましいです。
エクササイズ部分に当たるバー・アスティエクラスでは、カンブレ、エポールマン、ディベロペ、フェッテ・アラベスクなどを取り上げますので、この内容を取り組める方が望ましです。大人の生徒さんの場合は、基礎レベルのクラスを受けている方が安全に取り組めると考えます。
プログラム詳細 申込方法
レッスン開講可能日月曜日~木曜日・もしくは日曜日
※研修会・講習会・学会参加など、既にあんじゅの予定が決定している日程は受付ができません。
受講者数 最大15名まで
その理由)
感想にあるように、できるだけ一人ひとりの関節やカラダの部位に触れることがこのメニューのポイントです。そのため最大でも15人以内が望ましいのです。
時間帯
おおよそ、以下の時間帯で受け付けますが、お教室の日程と合わない場合は、具体的な希望時間をお伝えください。午前 11時~
午後 14時台
午後 16時台
午後 19時台
予約申込方法
2ヶ月前の同日・午前11時から、メールで受け付けます。
例)1 3月10日19時台希望の場合
→1月10日11時から受付開始 (※受付終了 1月31日21時)
例)2 5月29日14時台希望の場合
→3月1日11時から受付開始 (※受付終了 3月31日21時)
※注 受付有効期限があります。
クラスを実施する際には、治療予約の受付が不可となります。そのため、出張レッスンの受付は、2ヶ月前に開始、その月の末に終了となります。
例)3月10日19時台希望
→1月31日21時までが受付有効期限となります。
プログラム費用
1回 36,000円
+新宿駅からの運賃(実費)
時間 90分~120分
(お教室のレッスン時間に極力あわせます)
骨格模型は、ある程度形はしっかりしていますが、カートで長時間移動することは難しいため、駅からの徒歩が長いスタジオの場合、(目安10分以上の徒歩)タクシー代が必要になるケースがあります。ご了承ください。
お支払い方法
当日現金支払い
事前振り込みも受け付けます。後日振り込み口座をお知らせします。
ご予約お問い合わせはこちら