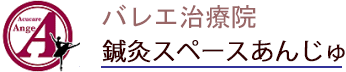効果的なストレッチの方法-フロアバレエ講師が解説します
昨日質問されたことがありました。その内容はとっても大事なので、こちらでも紹介しますね。
お題は「ストレッチについて」です。

この時は、バーが終わった後のリンバリングをどうとらえるか?についてでした。
バーレッスンが終わった後、生徒達はそれぞれカラダをほぐしますね。
今このストレッチについて、『やったほうがいい』『イヤ、やらない方がいい、やる必要がない』という両面からの説が言われていて、現場の先生方が悩んでいるようなのです。
海外で教えてきた先生や準プロクラスの生徒を教えている先生には【ストレッチ不要論】を言う先生もいます。
確かに既にカラダができあがっていてバーレッスンで必要な筋肉がしっかり使えているならそれでいいでしょう。
日本のお稽古場で指導されている先生としては、カラダの柔らかい生徒ばかりでなないのにどうすればいいのか?ということなのです。
もちろん、日本にも長年訓練を続けてきてバレエ団にはいるだろう先が見えている生徒が中心のお稽古場もありますね。
例えば、新国立劇場のバレエ研修所を代表とする専門性の高いところにある場であれば、上記のような【ストレッチはなくていもいい】が当てはまると考えられますね。
でも、多くのお教室にはいろんな生徒がいて、カラダの条件もそれぞれなことがほとんどです。
その場合、どうすればいいのか?という質問に対して、【ストレッチは筋肉を余計に伸ばしすぎるので必要ありません】は、実用的ではありません。
ではどうすれば良いのでしょうか?
ストレッチもカラダのしくみが土台
それは、カラダのしくみから診ること、がヒントになります。
カラダの仕組みとカラダの個性(タイプ)から診る
そもそもクラスが始まる前、又、バーが終わった時、どういうカラダの状態でいるのが理想的でしょうか?
レッスン前
目的はウォームアップです。
レッスン前であれば、カラダがある程度温まっていて、筋肉にも伸びが出て、プリエ・タンジュでかちこちにならないようにさせておきたい訳ですよね。
だから、そうなるようなメニューがいい訳です。
さて、カラダを診ると、筋肉だけじゃない、関節や靭帯・腱もあります。
特にカラダが温まっていないときは、いきなり大きな筋肉からストレッチをぐいぐいかけると筋肉は緊張度がアップして、逆に後で固まってしまいやすい。これを作用・反作用、と言います。
だから、教室に入ってきて、いきなり2番プリエで左右の脚をぐいぐい伸ばす、ようなことをやるのは、実はもったいないんです。
但し、クラスの前に充分なウォームアップしているなら別ですが、学校から急いで駆け込んできた後などにやるのは、カラダ的にはtoo much。
クラスが始まる前
カラダの各部位が動きやすいようにストレッチでほぐす
手首、足首など、遠いところから少しずつ回したりしてほぐしていき、カラダが温まってきたなと感じたところから、ストレッチをしていけば、カラダの硬いジュニアでも伸びていきやすいですね。
では、柔軟性が高い子は、どうすればいいのか?
柔軟性があるタイプにオススメストレッチ
これもカラダを診ると見えてきます。
柔軟性がもともと高いタイプは、筋肉だけじゃなく、関節・靭帯なども柔軟性があるので、ストレッチは楽にできます。
ただ、柔らかいからとストレッチで引っ張りすぎると、余計に引き伸ばされすぎて、逆に軸にまとめるのが大変になります。
柔軟性が高いタイプは軽い筋トレを加えたメニュー
がオススメ。
腹筋、背筋、側近、足裏など、レッスンで意識したいところを重点的に意識して筋トレし、その後更にストレッチをいれるのがオススメです。
では、バーが終わった後のリンバリングの時間は、どう指導すればいいのか?
バーが終わった後のストレッチ そのオススメ
ですが、これも、カラダを診ると見えてきます。
バーを一生懸命やりすぎるタイプは、どちらかというとカラダがカチコチになりやすいですね。『息を止めないでね』と言っても、踏ん張ってしまうタイプ。
そういうタイプは、ストレッチしていいのよ、と言っても、膝を抱えて休んでいたりします。あんまり、開かないカラダを見せたくないと言うタイプもいるでしょう。
カラダが硬いタイプは、筋肉よりも関節にフォーカスする
といいのです。
足首をほぐす、膝を抱えて股関節を回す、手首、肘、肩や首を回して上半身の力みを緩める。
関節がほぐれると、関節についている筋肉の緊張もほぐれて伸びやすくなるんです。膝を抱えて待っているよりずうっとお得(^_−)−☆
では
柔軟性がたっぷりあって、バーレッスンで十二分にカラダが伸びているタイプは、上記にあるように、更にストレッチをかけるのは、逆効果になるケースもあります。
カラダが柔らかいタイプは、ストレッチポールやボールなどで、殿部からハムストリングの間、脊柱の横をゆるめる
のがオススメです。
少し軽い腹筋入れるのも良いです。特に、カンブレでたっぷり反ったりした後は、インナーの腹筋を再確認させておきたいからです。
アップやリンバリングで抑えておきたい大切なふたつのこと
①場を考えること クラス前なのか、バーの後なのか これから何が必要なのか?がポイントです。
②カラダのタイプ考えること 柔軟性がタップリあるのか?どちらかというと筋肉や関節がかたまりやすいのか?
まだ自分で判断できない小学生低学年中学年のクラスでは、一斉の同じストレッチメニューをおこなうのが一般的ですが、硬くてカエルや前屈が苦手な子に同じことをずっと繰り返させると、必死にがんばろうとするあまり柔らかい脊柱に負担がかかって側湾症の元になったりする危険もあります。
そのようなケースのジュニアには、別に上半身のスクエアを意識させるエクササイズで補強してあげると、早く成果が出てきます。
日本のお稽古場には、いろんなタイプの生徒がいます。
先生達が育った時代よりも、更にいろんなタイプの生徒が増えているため、先生方の悩みも多様化しています。このようなストレッチについて、また、ケガをしやすい生徒へのアドバイスなど、バレエの解剖学【バレエアナトミー】で受け付けています。
>>>電話:090-9362-0080