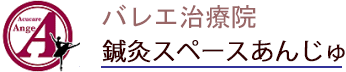後ろ手持ち 脚を放り投げなくてもできる|美しく安定して決める3ステップ練習法
新体操の後ろ手持ちやフィギュアスケートのビールマンスピンなど後ろにあげた脚を背中の高い位置でキャッチする技があります。
後ろ手持ちの練習でよくおこなわれているのが立って練習する方法。
背中の高い位置で脚をもつ技は、上へのベクトルが大切です。
なのに軸脚をふんばろうとする力は逆に下へのベクトルをつくりやすいという面があります。
そこでオススメなのが、こちらの3ステップです。
後ろ手持ちを完成させる3ステップ

するための3ステップとは
<目次>
ステップ①床での背筋+後ろ手持ち
ステップ②ベッドパンシェ+後ろ手持ち
ステップ③壁を手で押して後ろ手持ち
立って行う後ろ手持ちの難点とは
ステップ①床での背筋+後ろ手持ち

支える力も大切です
背筋のトレーニングの要領でうつぶせになって、脚をあげてから膝を折り畳みます。
そこからまず、片方の手で足を持ち、反対側の手で追いかけるように足をもつ。
この練習を繰り返します。
ポイントは2つ
- 背中を反らせる時に、腰に力が入ったままだと脚はあがっても膝を折り畳む時に脚が落ちるので注意すること
- 利き手ではない方(大抵は左)は床をしっかり押し上げる力が弱いので、肘がひっくり返らないように注意すること
①のステップ 背筋からの後ろ手持ちがすんなりできるようになったら、次のステップへ
ステップ②ベットパンシェから後ろ手持ち

次に膝を折って脚を持つへ

していきます
両手をついて押しあげられるくらいの高さ(60~75㎝くらいがベターです)の台を両手で押しながら脚をあげます。
両手を前に少し滑らせながらカラダを前に移動させ脚をあげていきます。
後は、①と同じであげた脚の膝を折り畳んで、片方の手で持ち、反対側の手で追いかけるように足をもつ。
ポイントは2つ
- カラダを前に移動させる時に首を折らずに胸を上げるようにすること
- あげた脚を折り畳む時に背中の高い位置で折り畳むようにすること
このベッドパンシェで、軸脚と腕でカラダを引き上げる感覚を探していきます。
②のステップ ベッドパンシェからの後ろ手持ちがすんなりできるようになったら、次③のステップ
ステップ③壁を手で押して後ろ手持ち

移ります
壁押しプッシュアップの要領で両方の腕で体幹を斜め前に押して、脚を後ろにあげます。
その状態からあげた脚の膝を折り畳んで、片方の手で持ち、反対側の手で追いかけるように足をもつ。
ポイント
- あがる脚の角度に従って、手は壁を滑らせて背中にボールがのるようなカーブができるようにします
この3ステップの後に、どこにも捕まらないで両足立ちから後ろ手持ちを練習すると、すんなり完成していきます。
立っておこなう後ろ手持ちの難点とは?
一般的に練習されている後ろで持ちの難点はこれです。
あげた脚の位置を探そうと手がぶれてしまう
手がぶれると体幹もぶれて、軸脚が不安定になってしいます。
床からベッドや台、そして壁とカラダを安定させたところから自分の脚があがっている位置を腕でもつ練習を繰り返すと、腕がぶれずに脚をキャッチできる様になっていきますよ。
立ったままの後ろ手持ちの練習でなかなかうまくいかないタイプはこの練習方法を試してみてください~
他にも参考になるコラムはこちらから
>>>部活で新体操を始めたジュニアのバックルが改善した例をご紹介
【著者プロフィール】
市川淑宥子(ようこ)
バレエ治療院あんじゅ院長
日本バレエワークアウト協会理事
鍼灸師/フロアバレエ・バー・アスティエ講師/チェアバレエエクササイズ講師
2008年、当時はなかったバレエ・ダンスのための鍼灸治療をスタートさせ、「バレエ鍼灸」と名付ける。現在も踊りを続ける治療家として、施術・ターンアウト改善、開脚改善などを展開。
骨格の見立てとフロアバーを通して、“カラダの内側センサー”とカラダのイメージの書き換えをサポートしています。
著書:『骨盤が立てばあなたの開脚は変わる』
フロアバレエクラス:新宿にて月1回開催中
▶ プロフィール詳細はこちら
▶ Instagram:ballet.ange
本記事では、著書『骨盤が立てばあなたの開脚は変わる』の筆者が、骨盤を立てるエクササイズと開脚改善のポイントを解説します。