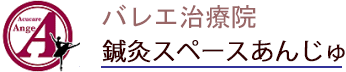解剖学―骨盤と大腿骨(股関節の可動域)①
分かりにくいと言われる解剖学をあんじゅ独自の視点でお届けするのがこの解剖学コラムです。【動かす(踊る)ためにカラダはどんな特徴があるのか?】を軸に人のカラダの仕組みを一緒に見ていきましょう。
骨盤と大腿骨が作るのが「股関節」です。この関節がどのくらい動くのか?
これを可動域と言います。
とても関心が高い股関節の可動域について、解剖学で取り上げます。
股関節可動域はどうやって調べる
股関節の単純な可動域は、仰向けやうつ伏せの姿勢でチェックすることができます。
仰向け(またはうつ伏せ)の状態で、膝を折りたたんで股関節から外旋させる
この可動域チェックで、45度(一般的な可動域)以上あると分かっても、それが=ターンアウトができる、につながらないケースが非常に多く診られます。
それは、10代のジュニアだけでなく、成人した大人の方も同様なのです。
どういうことかというと、可動域はあるのに骨盤を立てて開脚できない、カエルストレッチでお尻が上がる、プリエで膝がインになりやすい、ということです。
股関節の可動域があればターンアウトが完成しやすいのかと思ったらそこに落とし穴があるのです。
それは股関節の可動域とターンアウトが=ではないということです。
可動域はあくまで関節の条件、状況でターンアウトはムーブメントである
ということです。
そこでムーブメントであるターンアウトを知る前に、股関節の可動域とは何なのかをおさらいしておきましょう。
骨盤と大腿骨については
以下の記事を参考にしてください。
【バレエ・ダンス専門の臨床歴:踊る・診る・教えるの3つの柱】
- バレエ歴:25年(ダンス総合歴33年・今も踊り続ける治療家としての身体感覚)
- 治療歴 :19年(バレエ・ダンス専門治療院あんじゅ院長・腰椎滑り症の診断をきっかけに治療の道へ・2008年バレエ鍼灸を創始)
- 指導歴 :13年(運動療法の必要性を感じBarre au Sol バー・アスティエの資格取得2013年)
- 著書 :骨盤が立てばあなたの開脚は変わる(2021年出版)
- 役職 :一般社団法人日本バレエワークアウト協会理事
【専門領域】
筋肉中心の解剖学では解釈しきれないアンシェヌマンやステップを踊りやすくさせるアプローチが持ち味。(内部感覚+文化背景とBarre au Solのペタゴジーが土台です)
プロの極限まで使われたカラダ、ジュニアの成長期による変化からくるやりにくさ、大人の女性が気づきにくいカラダの変化によるやりにくさを診てきました。