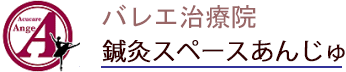ヴァリエーション改良中 (2)
現在、ヴァリエーションを改良中のジュニア。
パは全部こなせていて、通しのビデオでも踊れているのは分かります。
けれど、本人的には、足りない。
先生にも、もっと慌てない、余裕をもって、と言われる、周りからも後少し溜め、があればいいのに、と言われる。
でもどうすれば、、、、と悩んでるんですね。いろいろ試しているのは、沢山撮ってある動画の幾つかを見せてもらえば直ぐ解ります。
そして、一番最初に撮った時よりは、確実に格段に良くなってるのも明らか。
言われていることは分かっているのに、それをどう消化して、結果につなげるかで、もどかしい時、原因は、ほとんど下半身にあるんです。
簡単なステップですら、すべて脚の力だけで頑張ろうとしてしまっているんです。
これは、良くやってしまいがちなドツボ路線、、、、私自身、そういう経験は山ほど有ります^^;
こういう時には、フロアバーのテクニックや基本の筋トレ系エクササイズをするよりも、もっと効果的な方法をよくやります。
それが、『ちょいコンテンポラリー系な体重移動』を繰り返してみること。
クラシックバレエもコンテンポラリーも、体重移動はとても大切。けれど、決まったパがなく、カラダの自然な(時には不自然な)流れや動きを展開させていく系が多いコンテンポラリーと比べると、クラシックは決められたパで構成された中で体重を移動させていく。
全てはバーレッスンとセンターレッスンでやっていることが土台なのだけど、作品の中の踊りとなると、何故だか形を見せなければと固まってしまいやすくなります。
フェッテ・アラベクスとか、エカルテからのファイイとか、作品の中でやる方がちょっと緊張します。
緊張がカラダにあると、動きが固まって、脚だけでバタバタしやすい。本人はそんなつもりはないのに、何故かこじんまりとしてしまう。
なので、決まったエクササイズではなく、手足をカラダを大きく使って動き回る、をやってもらいました。
要は、コンテンポラリー系のレッスンでやるゆっくりとした体重移動です。
えっ?
クラシックのヴァリエーションなのに?
ハイ、なのに、です(^ ^)
普通、作品を練習している時は、そんなことはできませんが、パーソナルセッション【ターンアウトアップ】は、カラダをつくるためのトレーニングなので、こういうこともやれてしまうのです。
今回とりくんだこのコンテンポラリー系の体重移動、最初は、クラシックダンサー特有のぎこちなさがあってどう動いたらいいのか、、、みたいな感じだっのが、何度も繰り返すと若い力がムクムクっとあわられてくる。
どんどん、動きに滑らかさが出てきて、気がつくとコンテンポラリーで大切なカラダ全体をつかった体重移動ができるようになってくる。
カラダ全体をつかった体重移動、クラシックバレエでも同様に大切ですよね。
でも、一つひとつのパをちゃんとやらないと、ばかりになっているとどうしてもパだけを追うような動きになってしまう。
クラシックバレエはパで構成されていても、動きそのものは滑らかでなくては作品にはならない、その根本はコンテンポラリーとも共通しているのです。
この体重移動を繰り返しやった後の、動きは、下から上へのアプロンがしっかり感じられるものに変化。
本人も、ちゃんとのれてる感をしっかり体感していました。
最後は、これを自習でやるコツ、方法を伝授しました。ヴァリエーションに取り組んでいるとどうしても、繰り返し一曲を踊ることばかりやりがち。
うまくいかないところがあると、その部分だけを繰り返しやっても、カラダと脳がうまくつながっていない時は空回りになるんです。
そういう時に、このような体重移動の確認方法を知っていると、効果的に自習ができるのです。

コンクールサポートはこちらから
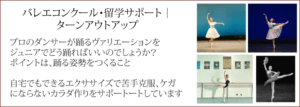
【バレエ・ダンス専門の臨床歴:踊る・診る・教えるの3つの柱】
- バレエ歴:25年(ダンス総合歴33年・今も踊り続ける治療家としての身体感覚)
- 治療歴 :19年(バレエ・ダンス専門治療院あんじゅ院長・2008年バレエ鍼灸創始者)
- 指導歴 :13年(フロアバレエ講師・一般社団法人日本バレエワークアウト協会理事)
- 著書 :骨盤が立てばあなたの開脚は変わる(2001年出版)
- 役職 :一般社団法人日本バレエワークアウト協会理事
【専門領域】
解剖学的な知識に留まらず「アンシェヌマンで動きやすい身体感覚を統合する独自アプローチ」を専門としています。大人リーナやカラダの硬いジュニアの「一生懸命なのに動きにくい」の背景から分析して施術。日仏露独のカンパニーダンサーから、ジュニア、大人まで幅広い臨床歴があります。