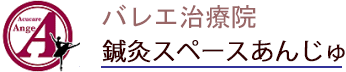ジュニアアスティエ講習会終わりました
3月末に続いておこなったバレエジュニアのための講習会。
本日4月3日は、バー・アスティエのクラスを行いました。
参加したジュニアの皆さんお疲れ様でした。
プロで踊っているダンサー達だけでなく、現在のジュニアも股関節の可動域は充分あります。けれど、ケガに泣くことがとても多い。もちろんテクニック習得過程の段階にいるのと終了したのとでは同じではないのですが。
それは、何故なのか?理由は
開くこと、これに固執しすぎるから
なのです。
日本人は、バレエ発祥の国に住んでいる人たちと同じ骨格ではありません。現在では体型が変わり、手脚が長くなっていると言われても、同じにはならないのす。それは民族自体が同じではないから。
骨盤の形も違うし、体幹の長さも違う、下腿の骨のラインにも違いがあります。
その土台の違いを分かった上で、コントロールして踊っていく。それがケガなく、開きやすいカラダをつくっていくコツでもあります。
そのために、ポワント講習会同様、レッスンの前に解剖学の時間を設けました。
骨の名前や筋肉の位置を覚えることが解剖学ではありません。
踊るために大切なのは、人のカラダがどういう構造になっているか、これを掴むこと
です。
何故必要かというと、ボディーイメージを掴むことが踊るために大切だからです。
ボディーイメージが掴めてくると、アンドゥオールが股関節だけでつくるものではないと言うのが分かって来ます。
実はそこからが出発点。
今日参加してくれた彼女達は、コンクールの予選を突破したり、受賞したり、夏のサマークラスに参加するなど、比較的経験を積んだジュニアでした。でもまだまだ自分たちのボディーイメージが掴み切れていないのです。
クラスが進みにつれて、ふっと力が抜ける、楽につま先が伸びる、力を入れなくてもアンドゥオールしていく、背中が伸びていく自分のを感じてくれているようでした。そして、そういう瞬間のラインは立体的で、本当に美しいのです。
バレエの解剖学と合わせて体感した「楽に伸びていく感覚」 それが彼女達のカラダを変えていくきっかけになっていって欲しいと思います。
この春は、10代前半までのジュニアを対象におこなった内容の基本は、バレエ治療院あんじゅのメニュー「ターンアウトアップ」。留学を控えたジュニアのボディーコントロールから、ケガをしたダンサーのボディーコントロールまで、パーソナルでおこなっているからこそ多岐にわたった内容をおjこなっています。
踊るカラダのバランスを取り戻すためのメニュー、土台はバレエの解剖学とバー・アスティエです。
【院長プロフィール】
市川淑宥子(ようこ)
バレエ治療院あんじゅ院長
○毎月一回フロアバレエクラス開催中
カラダが引き上がって脚が軽くなっていきます。一緒に踊ってみましょう~
○トレーニングメニュー【ターンアウトアップ】と【バレエの解剖学】から開脚の本ができました。
『骨盤が立てばあなたの開脚は変わる』
○踊りやすい、動きやすいカラダについて解剖学の外部講師活動もおこなっています。(活動レポート)