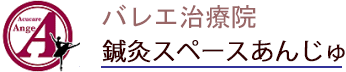踊り続けたい!をサポートするバレエ・ダンス専門治療院|フロアバレエ指導歴12年目の院長がケガや痛み、苦手解消をサポート|東京・代々木・バレエ治療院あんじゅ
インストラクター更新研修を担当しました
5月21日日曜日!
今年も日本バレエワークアウト協会の指導者更新研修を担当しました。
今回のテーマは、「バレエワークアウトの効果を人のライフサイクルから解剖する」でした。
ダンスやエクササイズする人口は増えていて、バレエ人口は40万人*1、ストリートダンス人口は600万人*2、と発表されています。
今の日本でバレエやダンスをしている人口、世代は広がっているんですね。
今回は、スライドで資料を用意して、人のカラダはどう変わっていくのか?を学んでいただきました。
沢山の世代がバレエ・ダンスを楽しんでいる。そのためには、何よりケガをしないこと、そのためには何が必要か、このようなことも解剖学では大切なことなのです。
このバレエワークアウトは、ニューヨークシティバレエ団のピーター・マーティンスが開発したエクササイズ。
バーは使いませんが、プリエ・タンジュから始まるセンターワークの後に、腹筋、背筋などの筋トレも入っているので、カラダ全体が鍛えられます。
その後にはダンスパートもあります。今年は、私も参加させていただきました。
今回は、ドンキホーテのキトリとウエストサイドストーリーでした。
*1日本のバレエ教育に関する全国調査 2012
*2一般社団法人ストリートダンス協会情報
【著者プロフィール】
市川淑宥子(ようこ)
バレエ治療院あんじゅ院長
日本バレエワークアウト協会理事
鍼灸師/フロアバレエ・バー・アスティエ講師/チェアバレエエクササイズ講師
2008年、当時はなかったバレエ・ダンスのための鍼灸治療をスタートさせ、「バレエ鍼灸」と名付ける。現在も踊りを続ける治療家として、施術・ターンアウト改善、開脚改善などを展開。
著書:『骨盤が立てばあなたの開脚は変わる』
フロアバレエクラス:新宿にて月1回開催中

関連記事
2025年5月30日