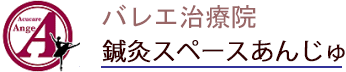出張講座、バレエの解剖学+フロアバレエ
バレエの解剖学+フロアバレエの出張講座に行ってきました。
今回お呼びいただいたのは、K先生のお教室。小、中、高校、大学生から大人の方まで参加してくれました。
この講座では最初、小学生でもイメージしやすいように解剖学用語は使わずカラダの仕組みとバレエの姿勢について、骨模型を使って解説していきます。
例えば、アラベスクの手を解剖学的にどう見ると先生がいつもおっしゃる『鼻の前に手』になるか、何故上手くいかないのか、など、自分のカラダを使ってもらいながら解説する部分も作っています。
というのも、先生の教えが上手く咀嚼できないのはそれぞれのボディイメージがクリアではないから、なんです。だから、自分自身のカラダで考えてみなくては、なのです。
カラダの仕組みとバレエの姿勢の関係性をつかんでもらってから、バレエの股関節、バレエの膝、つま先を伸ばす時にどこを使うのか?を解説していきます。
皆さんもここが一番気になる所なんですが、最初にこれから話してしまうと、結局パーツだけで動かすことになってしまう。それではカラダ全体を使って踊るバレエにはならないんですね。
大切なのは全体性。
膝を伸ばしたいからとお膝のお皿を押して立つと結局膝は伸びないこと、脚を開きたいと足指に力を入れて踊っていると脚が太くなっていくこと、などもカラダの仕組みと合わせながら解説していきました。
その後、フロアバレエ・バー・アスティエの基礎エクササイズにトライ。
解剖学講座の部分で解説したボディイメージと姿勢を作るためのキーポイントを意識しながら踊ると脚の力が抜けていくことを少〜し実感してくれたようです。
力ではなくカラダ全体でアンドゥオールを作ると膝も伸びるし脚も軽くなってつま先も伸びる
ボディイメージがクリアになってくる時は『あれ?エッ〜』と表情が変わる瞬間でもあります。
先生も生徒さんのボディイメージをクリアにしようと色々な言葉で教えていらっしゃるんですが、それがどうにも伝わっていないんじゃないか?な時、外からの視点を入れてみると、生徒さんも『そうだったのか?』を見つけやすくなります。
バレエの解剖学講座は、最近ではいろんな所で開かれていますが、講座だけだとどうしても頭の理解で終わりがちなんですね。
聞いている解剖学が具体的に自分のカラダとどうつながっているのか?そこが大事なんです。
だからこそ、その後にフロアバレエにトライする意味があるのです。
バー・アスティエは床に座って寝てエクササイズをしますが、その源はクラシックバレエ。
カラダの仕組みとバレエのムーブメントがつながっていることを体感してもらえる、それがこの、出張講座『バレエの解剖学+フロアバレエ』です。
>>>電話:090-9362-0080