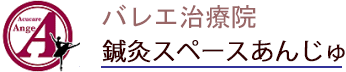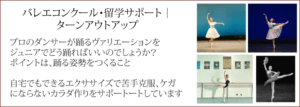ただいま、ヴァリエーション改良中 (1)
現在ユースアメリカングランプリ日本予選真っ最中ですね。今年は、このコンクールに出るクライアントはいませんが、年末年始のコンクールに参加するジュニア達のヴァリエーションをブラッシュアップしています。
と言っても、ここはお稽古場ではないし、全体の指導はそれぞれの先生がなさること。
私がターンアウトアップで見ているのは、踊りを支えるカラダの使い方です。
中学生だと、アラベスクターン、アティチュードターン、イタリアンフェッテやグランパデシャなど、作品の中の大技的な部分を脚技的に捉えてしまいがち。
例えば、
イタリアンフェッテで、どうしても高く脚が上がらないんです、、、
ピルエットで、3回転できなくて、、
グランジュッテで、大きく飛びたいのに、、
などが悩みなんですね。
でも、これらは全て脚中心に考えてしまうからうまくいかないことがほとんどと言っていいんです。送ってもらった動画を見ても、やはり脚でなんとかしようとしているのがありあり。
一歩引いてみれば、自分でも気づくはずなのに、練習している最中にはどうしても見えないことが多々あります。
この時にやっていることを今回は紹介します。
ターンアウトアップでおこなっている内容とは
例えば、アティチュードターンで、脚が上がらないし、重くなる時、何度も同じ部分をさらっても結局いい結果は出ません。カラダと脳は負のスパイラルにはまりつつあるから。
なので、シンプルなエクササイズを組みます。
・体幹を意識して床でフェッテする(フロアバレエ)
・ポールドブラだけで動いてみる
・基本中の基本、体幹トレーニングに戻る
アティチュードターンでは、どうしてもあばらが開いてしまいがち。しかもピルエットと違って動作脚は後ろにあるのでボディをしっかり立てておかないとバランスは崩れやすい。
アティチュードだけなら、容易にできることも回るとなるとどうしても力が入りやすいんですね。
今回は、床でスゴンからのフェッテ、アラベスクにしっかり決め、腕でしっかり支えて軸脚に乗れる感覚を養うフロアバレエエクササイズを何度も繰り返しました。
バー・アスティエの土台はバレエなので、バレエの基本を確認できるエクササイズがたくさんあります。
その後直ぐアティチュードターンをやるのではありません。ピルエットアンデダンで、しっかり上に抜けて回る感覚を再確認しました。
何故って、種類は違っても、土台は同じだからです。エポールマンをずらさず、体重移動をしっかり確認したうえで、ボディを引き上げて回る感覚が回転には必要だから。
崩れたら、又、最初のエクササイズに戻る、これを何回かを繰り返すと、少しずつカラダの感覚がつかめていくんですね。
途中、うまくいかない時は、もっとシンプルにアラベスクパンシェをすることも。
アラベスクも脚だけをあげようとすると、体幹はぶれてしまいます。
しっかりボディをコントロールして、軸脚に体重移動ができた上でパンシェをする感覚は、アティチュードターンにも必要です。
ターンアウトアップの内容
・ボディコントロールのエクササイズをおこなう
・基本のパを分解したエクササイズをする
・カラダのどこがどう意識できていないのか?を確認する
このようなことをおこなっています。
ヴァリエーションの一人自習だと、どうしても一曲さらって、又、繰り返して、なんでうまくいかないんだろうと、、になっていく。
これが負のスパイラルにはまってしまう所以。
決めたい大技も全てバレエの基礎のパが土台ですよね。そして、そのパを完成させるためには体重移動や引き上げなど、ボディコントロールが欠かせません。
当たり前なんだけど、渦中にある時は、そこが見えてない。そこに目を向けさせることがポイント。
彼女達のチャレンジはまだまだ続きます。変化はアップだけでなくダウンもある。でも、どこを意識するかに気づけたら、一人でやる自習も内容が変わっていくのです。
まだまだ改善中。その中で、単に回ったり飛んだりじゃなく、カラダをコントロールして踊りを作っていくことを体感してほしい。
がんばれ〜